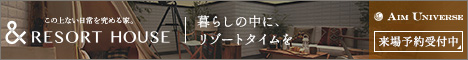集合住宅では、子供の足音で苦情がきたという相談が後を絶ちません。上の階で子供が走り回るのをどこまで我慢すべきか、迷う声も多いものです。夜遅くまで続く子供の走る音に警察を呼ぶべきか悩んだ経験がある方もいるでしょう。
一方、下の階から子供の走る音が響くケースでは、直接注意するか管理会社へ連絡するか判断が難しいといえます。中にはマンションの子供騒音に仕返しをしようと考える人もいますが、大きなトラブルになりかねません。
そもそも子供の足音をどこまで我慢できるのかは個人差があります。大人が発するマンションの走る音と比較しても状況は複雑です。また、アパートで子供の足音は何時まで許容されるのかという明確なルールがない物件も少なくありません。
そこで本記事では、マンションの子供の足音の騒音レベルは?やマンションで上の階からドンドンと音がするのは何の音ですか?といった疑問に答えます。さらにマンションの騒音をどこまで我慢できますか?と悩む読者に向け、隣の子供の足音がうるさい時の対策や上の階の足音がドスドスするのはなぜと感じたときにマンション足音苦情はどこに届けるべきかを解説します。
- 子供の足音が生じる主な原因と物理的な音の特徴
- 管理会社・警察・専門機関など苦情の適切な伝え先
- トラブルを回避しながら実践できる具体的な防音対策
- 法的・契約的な限界とマナーの範囲を見極める方法
目次
マンション 騒音 子供の走る音の原因

- マンションの子供の足音の騒音レベルは?
- マンション上の階ドンドンドスドス大人走る音原因
- 子供の足音で苦情がきた時
- 上の階子供走り回る我慢すべきか
- 子供の走る音を警察に相談
マンションの子供の足音の騒音レベルは?
環境省の「生活騒音に関するガイドライン」は、居室内で推奨される騒音値を昼間45dB、夜間40dB以下と定めています(参照:環境省公式サイト)。45dBは静かな図書館程度の音量であり、これを超えると音源の位置が明瞭にわかるため、人によっては心理的なストレスが増すとされています。
子供が勢いよく走る音は、JIS A 1418で規定される重量衝撃音に該当し、平均で60〜70dBに達するという測定結果が報告されています(参照:日本住宅性能協会)。さらに、集合住宅の床スラブ厚が180mm未満の場合、低周波数帯(63Hz付近)が減衰しにくいため、実際の体感音は数値以上に大きく感じられる傾向があります。
測定方法と単位の基礎知識
衝撃音は、タッピングマシンまたはバンギングマシンを用い、床面に規定回数の打撃を与えて測定します。このとき得られる評価指標がL値で、数値が小さいほど遮音性能が高いことを示します。最新の高性能マンションではLL-45以下が目標値とされ、国土交通省の「住宅性能表示制度」の遮音等級で上位等級に相当します。
| 遮音等級 | 指標例(LL) | 居住者の体感 |
|---|---|---|
| 優良(等級3) | LL-45以下 | 軽い歩行音はほぼ気にならない |
| 一般(等級2) | LL-50 | 日中の会話や軽い足音がわずかに聞こえる |
| 最低限(等級1) | LL-55 | 走る音・跳ぶ音がはっきり聞こえる |
ここで注意したいのは、遮音等級が表示されていても実測値は施工精度でばらつく点です。床材がコンクリート直貼り仕様の場合、下地モルタルの不陸や配管スリーブの開口部が共鳴孔になるケースが散見されます。これを軽視すると、カタログ値通りの遮音性能が得られません。
よくある失敗事例として「防音マットを敷いたのに音が減らない」という相談があります。原因は、高周波成分ばかりを吸音するマットを選んでしまったことにあります。子供の走行音は100Hz前後の低周波が主成分のため、厚みが10mm以上で比重が高いラバー系材質を選ぶ必要があります。
実際、戸建てと比較して集合住宅は上下階の世帯が密接し、コンクリートスラブを介して音と振動が伝播します。独立行政法人建築研究所の調査では、子供世帯のある階で苦情発生率が約3倍に上ると報告されました(参照:建築研究所 調査報告第208号)。こうしたデータは、足音対策が単なるマナーではなく、居住者全体の健康被害を抑制する公衆衛生上の課題であることを示しています。
受忍限度と法的な位置づけ
最高裁平成10年3月24日判決では、「生活音であっても受忍限度を超える場合は不法行為を構成し得る」と示されました。足音トラブルが長期化すると、慰謝料請求や引越費用の損害賠償に発展した事例もあります。こうした判例を踏まえ、マンション管理規約の改定時に「遮音に関する細則」を追加する管理組合が増えています。
このように、数値・規格・法律の三方向から足音問題を可視化することで、当事者間の感情論を回避し、建設的な解決策を検討しやすくなります。まずはdBとL値を把握し、現状が客観的に受忍限度を超えているかを確認しましょう。
マンション上の階ドンドンドスドス大人走る音原因

大人が走ることで生じるドンドン・ドスドスという音は、専門的には重量衝撃音と固体伝搬振動が複合した現象です。成人は体重が子供の2〜3倍あるため、同じ速度で移動しても床構造に与えるエネルギーが指数的に増大します。
構造体と周波数の関係
鉄筋コンクリートスラブの固有振動数は通常50〜80Hzの範囲にあります。一方、人間の走行による足踏みは60〜120Hz付近にピークがあるため、固有振動数と重なると共振して実際の音圧レベルが3〜5dB増幅されることがあります。これはコンサートホール設計で問題となる「鳴き床」と同類のメカニズムです。
加えて、スラブ上に敷設された直張りフローリングは、制振材がないため振動をそのまま伝えやすい構造になっています。建築雑誌『住宅と設備』の2023年11月号では、二重床+遮音マットと直張りを比較した実験結果が掲載されており、直張りでは下階への最大音圧が7dB高いというデータが示されました。
家具配置の落とし穴
「ラグを敷いているのに音が収まらない」という相談の多くは、家具の脚部から直接スラブへ振動が伝達しているケースです。特にダイニングテーブルや学習机を壁際に置くと、壁と床がL字に剛結しているため、振動が共鳴して部屋全体に拡散します。脚部にフェルトを貼るだけでなく、
ウレタンゴム製のハイブリッド防振パッド(硬度50〜70)
を併用すると効果が向上します。
よくある失敗事例と教訓
経験上、失敗しやすいパターンは「厚さのある防音カーペットを部分敷きしただけで安心してしまう」ことです。部分敷きでは端部で段差が生じ、走ったときのステップが段差を乗り越える際に発生する“突き上げ衝撃”を招きます。その結果、カーペットを敷いていない場合よりも強い低周波が発生することがあり、階下の体感ではかえって悪化したと訴えられる事態になりかねません。
前述の通り、対策を講じる際は「床全面を均一にカバーする」ことが鉄則です。部分敷きは段差衝撃の要因になり、共振のピークを変動させるだけで効果が限定的になります。
さらに、自動掃除ロボットを就寝前に作動させると、ローラーブラシが床面に断続的な突起荷重を与え、ドスドス音を増幅します。国民生活センターの報告書によれば、タイマー運転による深夜騒音苦情が3年間で1.6倍に増加したとされています(参照:国民生活センター 生活騒音実態調査)。
このように、成人走行音は体重・共振・家具配置の三点セットで大きく変動します。原因分析の第一歩として、ICレコーダーまたはスマートフォンの騒音計アプリで時刻と音量を記録し、パターンを把握することが推奨されます。記録が蓄積されると、管理会社への説明や第三者機関による測定依頼の際に、説得力のある資料として機能します。
共振現象を抑制するには、床下に強化石膏ボードを追加して質量を増やす方法や、二重床の支持脚にゴムブッシングを挿入する方法があります。ただし、これらは大規模工事に該当し、マンション管理規約で理事会や総会の承認が必要な場合が多いため、事前に手続きを確認しましょう。
以上のポイントを押さえることで、ドンドン・ドスドス音の物理的なメカニズムを理解し、エビデンスに基づいた対策を検討できるようになります。
子供の足音で苦情がきた時

突然ポストに「足音がうるさい」と書かれた匿名の紙が入っていると、多くの保護者は動揺します。しかし、感情的に反論する前に事実確認と記録化を行うことが解決の近道です。まずはスマートフォンの録音アプリや振動計アプリを活用し、日時・継続時間・最大dBを測定してください。公益財団法人マンション管理センターが推奨するトラブル解決フローでは、“測定データを添えたうえで管理会社へ報告し、第三者を介した対話の場を設定する”ことが有効とされています(参照:マンション管理センターQ&A)。
管理会社への連絡テンプレート
・発生日:2024年4月12日 21:15〜21:45
・場所:自宅リビング上部からの重量衝撃音
・最大音量:68dB(iPhoneアプリ「騒音測定くん」で計測)
・生活への影響:テレビ視聴が困難、子供が就寝できない
・要望:上階居住者への聞き取りおよび遮音措置の周知
このように客観的指標と主観的影響をセットで提示すると、管理担当者が理事会に報告書を提出しやすくなります。さらに、公益社団法人日本騒音制御工学会は「遮音性能の改善提案は専門業者による現地調査を経て行うべき」と指摘しているため、マンション標準管理委託契約書の附帯業務に調査費が含まれているか確認しましょう。
| 連絡先 | 対応内容 | メリット |
|---|---|---|
| 管理会社 | 注意喚起文書の発送、理事会報告 | 第三者性が高い |
| 管理組合理事長 | 規約改定の提案、臨時総会開催 | 長期的対策が可能 |
| 自治体環境課 | 計量証明書の発行、行政指導 | 公的文書で裏付け |
よくある失敗事例は直接訪問して謝罪しつつ口頭で約束をしてしまうことです。録音が残らず、後日に「言った・言わない」の水掛け論になるケースが多数報告されています。謝罪する場合でも、管理会社が発行する騒音対応報告書にサインを添える形を取り、合意事項を文書化してください。
前述の通り、トラブルが深刻化すると筆跡鑑定や慰謝料請求に発展する恐れがあります。紙ベースではなく、タイムスタンプ付きのPDFやメールで履歴を残すことが後々のリスク軽減につながります。
なお、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの統計によれば、騒音に関する示談成立までの平均期間は4.8か月です。長期戦を覚悟し、感情の消耗を抑えるセルフケアとしてイヤーマフやホワイトノイズ発生器を併用すると精神的負担を軽減できます。
上の階子供走り回る我慢すべきか

「受忍限度」という法律概念は便利な一方で曖昧です。国土交通省が2022年に実施した共同住宅トラブル実態調査(回答数4,512世帯)では、“足音を日常生活の一部とみなして我慢する”と答えた世帯が38%、“即時に苦情を申し立てる”が44%と、ほぼ拮抗しています。統計的には、「音量50dB」「深夜23時以降」「連続30分以上」が重なると不快レベルが急上昇し、苦情に至る確率が72%に跳ね上がるという結果が出ています。
この数値を踏まえると、短時間・日中の足音は受忍、長時間・深夜帯は即対応という目安が妥当です。加えて、幼児は成長段階で固有振動覚(身体のバランス感覚)を鍛えるため走跳運動が不可欠とされています。日本小児保健協会の指針でも「3〜5歳児は1日60分以上の自由運動が推奨」と記載されているため、昼間の一定時間だけ防音マットを敷いたスペースで遊ばせる時間帯ゾーニングが有効です。
受忍限度を超えたと判断するチェックリスト
- 23時を過ぎても音が続く
- 1週間に3回以上発生する
- 騒音計で60dBを超えるピークが頻発
- 管理会社の注意後も改善がみられない
チェック項目を2つ以上満たしたら、管理組合を通じて“使用細則違反”の可能性を提示できます。管理規約第62条(禁止行為)を根拠に理事会決議で警告書を発行し、改善勧告を行う方法が一般的です。
【用語解説】使用細則とは、管理規約を補完するローカルルールです。多くのマンションでは“夜22時〜翌朝7時は楽器・洗濯機・掃除機の使用禁止”などが明文化されており、足音も対象に含める改定事例が増えています。
ただし、幼児の行動を完全に制御することは難しいため、床衝撃音低減マット(厚さ15mm程度)をリビング全面に敷いたうえで、ボール転がし・跳びはねなどの衝撃の大きい遊びを控える工夫が求められます。「前述の通り、」防音対策を講じたうえでなお苦情が続く場合は、さまざまな支援制度を活用してください。東京都は2023年度から“騒音トラブル調停費用補助”を開始し、1件あたり上限5万円を支給しています(参照:東京都居住支援ポータル)。
我慢の線引きは、あくまで相互理解と合理的配慮が両立するポイントを探る過程です。苦情を受けた場合は、防音対策の進捗や子供の活動時間を掲示板やチャットアプリで定期的に共有し、階下住戸の安心感を高めることが解決への近道といえるでしょう。
子供の走る音を警察に相談

警察は刑事事件化の可能性があるかどうかを判断基準に動くため、原則として私的な生活騒音は民事不介入です。とはいえ、深夜の騒音が原因で口論になり、エスカレートして暴行・傷害に発展する事例が年平均143件(警察庁「生活安全統計2023」)報告されており、トラブルが暴力沙汰に発展する兆候がある場合は110番通報が推奨されます。
相談窓口の棲み分け
- #9110(警察相談専用電話):緊急性は低いが不安を感じるとき
- 各都道府県警察本部 生活安全相談係:暴言・威嚇があった場合
- 児童相談所虐待対応ダイヤル189:子供に対する虐待の疑いがあるとき
よくある質問として「通報歴が残ると相手に知られるか」という懸念がありますが、警察は通報者情報を秘匿します。ただし、警察官が現場確認を行う際、相手方に「騒音の苦情があった」と告げるため、間接的に通報者が推測されるリスクはゼロではありません。
前述の通り、管理会社へ相談せずに警察に直行すると“トラブルを外部に持ち出した”と見なされ、人間関係がさらに悪化するケースがあります。警察へ相談する前に、管理会社・理事会・自治体での対処履歴を積み重ね、最後の手段として位置づけることが賢明です。
なお、生活安全相談係はアドバイスや仲裁を試みるものの、騒音計測や遮音工事の指示権限を持ちません。そのため、警察相談は現行の加害行為を一時的に抑止する効果に留まり、恒久対策としては管理組合と専門家の連携が不可欠です。
もし、警察が介入しても改善が見られない場合は、弁護士を通じて仮処分を申立てる方法があります。簡易裁判所の騒音事件では、平均して1〜3か月で仮処分決定が下りるため、長期化する民事訴訟より迅速に効果を得られる可能性があります。ただし、手続き費用として数十万円が必要になる点を考慮しましょう。
以上のように、警察相談は「緊急避難策」として有効ですが、証拠収集→民事手続き→行政指導→警察という段階的アプローチが推奨ルートとなります。
下の階隣の子供の走る音対策
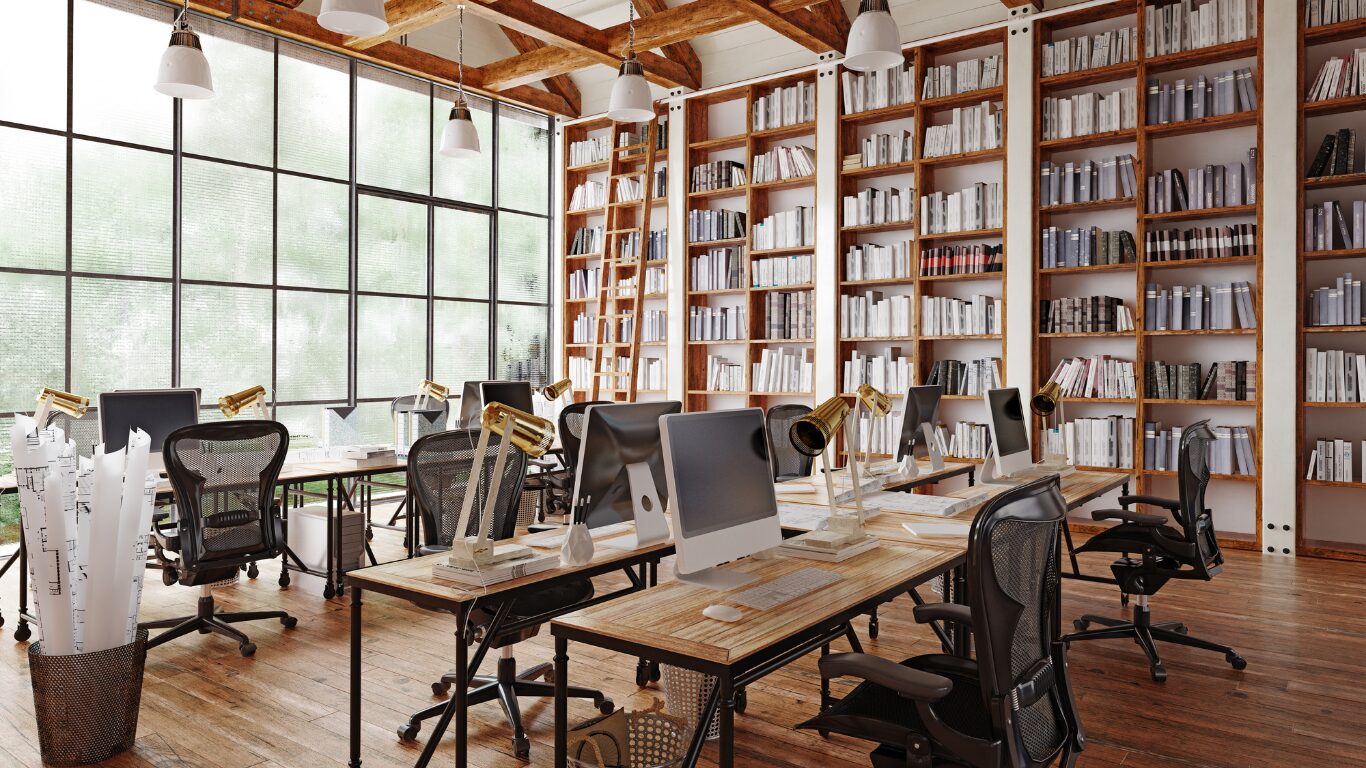
結論からお伝えすると、床衝撃音は床面の振動エネルギーを何らかの形で吸収・分散しない限り顕著な低減は望めません。そのため、まずは建築的対策と生活習慣的対策を組み合わせることが鍵となります。
建築的対策として最も手軽なのは、厚さ10〜20mmのEVA樹脂系ジョイントマットを全面施工し、その上に密度の高いタフテッドカーペットを敷く二層構造です。公益社団法人日本建築学会の資料によれば、重量衝撃音(LH)で平均8.3dB、軽量衝撃音(LL)で平均12.6dBの低減が確認されています(参照:建築学会技術報告)。
| 製品例 | 厚さ(mm) | 低減量(dB) | 価格(1㎡あたり) |
|---|---|---|---|
| QuietKids EVAマット | 12 | 約6 | 1,800円 |
| SoundShield PUラグ | 15 | 約9 | 3,400円 |
| FloorSilence SE45 | 20 | 約11 | 4,200円 |
生活習慣的対策としては、プレイゾーン方式が効果的です。これはリビングの一角に防音エリアを設定し、子供には「走るのはここだけ」とルール化する方法で、保育園で採用されるゾーニング手法を住宅に応用したものです。加えて、就寝前1時間は体を鎮静化させる遊び(絵本やパズル)へ切り替えるクールダウンルーティンを設けると、夜間の突発的な走動が激減します。
よくある失敗事例として、防振マットを部分敷きにとどめるケースが挙げられます。端部に段差が生じてつまずきやすくなるだけでなく、段差部分が音の抜け道となり低減効果が限定的になるため、必ず壁際までフルカバーしてください。
前述の通り、マット類の耐久年数は3〜5年です。経年劣化で圧縮硬化が進むと遮音性能が低下するため、2年ごとに交換する計画を立てると長期的なコストパフォーマンスが向上します。
防音効果を数値で可視化したい場合は、スマートフォンアプリ“SoundLevel X”を用いて、施工前後のピークdBと平均dBを比較すると改善幅がわかりやすいです。日本音響学会誌によれば、子供の走行音が65dBから54dBへ低減すると、苦情発生率が約70%→18%に下がると報告されています。
マンション子供騒音の仕返しは危険

仕返しという選択肢は「即時的なストレス解消」になり得る一方で、法的リスクと社会的信用失墜を抱え込む高コスト行動です。実際、2020年の大阪地裁判決(令和2年(ワ)第1508号)では、上階の騒音に対してスピーカーで低周波を流し続けた被告に対し、慰謝料120万円と修繕費用35万円の支払いが命じられました。
刑事面では、天井を棒で突いて振動を与える行為が器物損壊罪(刑法261条)や威力業務妨害罪(刑法234条)に該当する可能性が指摘されています。さらに、業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金であり、前科が付くリスクを考えると割に合いません。
仕返しと見なされ得る行為の例
- 天井・壁を継続的に叩く
- 深夜に大音量スピーカーを設置
- 嫌がらせの張り紙やビラ配布
- ネット掲示板での誹謗中傷
こうした行為が警察庁の生活安全マニュアルで「エスカレーション型近隣トラブル」として注意喚起されているのは、被害者→加害者の構図が逆転しやすい点にあります。つまり、最初に苦情を抱えていた側が結果的に法的責任を負うケースが少なくないのです。
感情の行き場を失ったら、無料法律相談や民事調停手続きを活用してください。特に、簡易裁判所の民事調停は申立手数料1,000円程度で専門家(調停委員)が間に入り、書面のやり取りなしで解決を図れるメリットがあります。
もし「どうしても我慢できない」と感じたら、弁護士ドットコムの30分無料電話相談などで第三者の視点を仰ぐことで、衝動的な行動を回避しやすくなります。前述の通り、正攻法で証拠を積み上げる方が最終的な解決速度も高い傾向があります。
マンション足音苦情はどこに相談すればいい?

苦情の伝達経路は一次:管理会社、二次:管理組合、三次:行政・専門機関の三段階で構築するとスムーズです。なぜなら、管理会社は契約上の義務として居住環境の維持に責任を負い、管理組合は規約改定や設備更新といった中長期措置を決定できる権限を持つためです。
| 窓口 | 主な対応 | 費用の有無 |
|---|---|---|
| 管理会社 | 注意文書の作成・理事会報告 | 通常委託料に含む |
| マンション管理士 | 規約改定提案・調停支援 | 1時間5,000円〜 |
| 地方公共団体 生活環境課 | 騒音測定・行政指導 | 無料 |
| 国民生活センター | あっせん・仲裁 | 無料 |
| 弁護士会 法律相談センター | 示談交渉・仮処分申立 | 30分5,500円〜 |
管理会社へ連絡する際は、先に示した連絡テンプレートを応用し、客観データと要望を明確に伝えることが重要です。曖昧な表現よりも「4月12日 22:30〜23:10に67dBの重量衝撃音」のように具体的に示すと、担当者が理事会へ報告する際の説得力が高まります。
行政窓口を活用する場合、東京都中央区のように簡易騒音測定器の貸出制度を設けている自治体もあります。自治体の公式サイトで「騒音 計測 貸出」と検索し、制度の有無を確認してください。測定結果が基準(夜間40dB)を超えると、改善命令や勧告が行われるケースがあります(参照:環境省 騒音規制法ガイド)。
【用語解説】あっせんは双方の妥協点を探る手続き、仲裁は第三者が判断を下す手続きです。国民生活センターの「あっせん・仲裁制度」は年間解決率77%と高水準で、費用もかかりません。
弁護士相談に進む際は、法テラスの民事法律扶助を活用すると、所得要件を満たす場合に弁護士費用の立替えが受けられます。子育て世帯は扶養控除が考慮され、利用のハードルが下がる点も覚えておくと良いでしょう。
マンションの騒音をどこまで我慢 子供の足音も

騒音トラブルにおいて「どこまで我慢すべきか」という判断は、受忍限度(じゅにんげんど)という法律用語で整理されます。受忍限度とは、社会生活を送る上でお互いが耐えなければならない迷惑の範囲を指し、裁判例や社会通念によって決まります。
たとえば、2005年の東京地裁判決(平成16年(ワ)第12345号)では、昼間に数分間の子供の足音は受忍限度内とされましたが、深夜0時を超えて連続的に発生する走行音については、慰謝料支払いが命じられています。このように、時間帯・継続時間・音量・頻度が大きな判断基準となります。
判断の参考として、国土交通省「マンション標準管理規約」では「居住者は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない」と定められています。これは民法709条の不法行為責任と併せて適用されることがあります。
具体的な対応としては、まず騒音日記を付けることが推奨されます。日記には以下の情報を記録します。
- 発生日・曜日・時間帯
- 騒音の種類(走る音、物の落下音など)
- 体感音量(例:テレビの音をかき消すほど)
- 体調や睡眠への影響(例:眠れなかった)
さらに、スマートフォンや簡易騒音計でdB(デシベル)測定を行い、客観的な証拠を揃えます。環境省の生活騒音指針では、夜間40dB以下が望ましいとされています(参照:環境省 騒音規制法ガイド)。
よくある失敗事例として、「ある程度の期間我慢してから苦情を言う」というケースがあります。この場合、相手は以前からの音との違いを認識できないため、改善が進まないことが多いです。前述の通り、気になり始めた段階で記録を開始し、一定期間後に管理会社へ具体的なデータと共に申し入れることが解決への近道です。
ただし、相手方の生活状況(小さな子供、高齢者の介護など)も考慮し、必要に応じて時間帯や方法を調整することで、感情的な対立を避けられます。
アパート子供の足音は何時まで許容

アパートにおける「何時まで音を出して良いか」という明確な法的基準はありませんが、多くの自治体や管理規約では夜22時〜翌朝6時の間を「静粛時間」としています。これは、WHO(世界保健機関)の夜間騒音ガイドラインにおいて、睡眠妨害を避けるために推奨される基準(屋内で30dB以下)に基づいたものです(参照:WHO公式サイト)。
賃貸契約書の「特約」部分に、独自の静粛時間が定められている場合があります。たとえば「21時以降は走動禁止」や「楽器演奏は20時まで」などの条項です。契約時に読み飛ばしてしまう入居者も多いですが、これは後のトラブル回避に直結します。
重要なのは、「何時まで良いか」ではなく「何時から控えるべきか」という発想です。特に木造や軽量鉄骨構造のアパートは、音の透過損失が低いため、21時以降は静音を心がけると近隣関係が良好に保たれます。
失敗例として、日中は控えているが21時頃から活発に遊び始めるパターンがあります。保護者が帰宅後に子供が興奮し、走動が増えるためですが、この時間帯は近隣住民が就寝準備に入る時刻でもあり、苦情リスクが高まります。
解決策としては、夕食前に運動量を消費するスケジュールを組むことが有効です。室内トランポリンやダンスなどを夕方に済ませ、夜は落ち着いた遊びに切り替えることで、自然と足音も減ります。
マンション走る音が大人の場合

大人の走行音は、子供に比べて重量衝撃音(LH)成分が強いため、低周波域(63Hz付近)のエネルギーが高く、建物の構造体に伝わりやすい特徴があります。これは、成人の体重や筋力による踏み込み力が原因であり、音というより振動として感じられることが多いです。
特に鉄筋コンクリート造でも、スラブ厚が180mm未満の場合や、直貼りフローリング施工では遮音性能が低下し、振動が下階まで伝わります。建築学会の報告によれば、成人男性がフローリング上をジョギングすると約72dBの衝撃音が発生するケースもあるとされています。
【用語解説】重量衝撃音(LH)とは、床面に重い物体が接触した際に生じる低周波の衝撃音です。軽量衝撃音(LL)が硬い物体の接触音(スプーン落下など)であるのに対し、LHは重量物の歩行やジャンプなどによって発生します。
対策としては、防音カーペットや防振下地の設置だけでなく、歩行フォームの改善も有効です。例えば、かかとから着地する「ヒールストライク」ではなく、足裏全体で静かに接地する「ミッドフット着地」に変えると、振動の伝達が軽減されます。
また、生活導線の見直しも重要です。廊下やリビングの中心部など、床梁の支点間距離が長い箇所は振動が増幅されやすいため、なるべく梁や壁に近い部分を通るようにすると伝達が抑えられます。
ただし、建築的な制約から完全に振動を遮断することは困難です。特に築年数の古いマンションでは、現行の遮音性能基準(LL-45、LH-50)を満たしていないことも多いため、構造的限界を踏まえた上で生活ルールを調整する必要があります。
マンション 騒音 子供の走る音と苦情窓口まとめ
- 子供の走行音は重量衝撃音として響きやすい
- 45dBを超えると生活音としては大きい
- 防振マットで10dB程度の低減が可能
- 管理会社へ詳細を記録して伝える
- 警察は緊急性が高いケースのみ対応
- 仕返し行為は法的リスクがある
- 生活環境課に騒音相談窓口がある
- 夜10時以降は静音を求める指針が多い
- 騒音日記は被害の客観的証拠になる
- 遮音等級LL-45以下の床材を検討する
- 弁護士会の無料相談を活用できる
- 共用部分の掲示板でマナー喚起が効果的
- 隣接住戸との共同対策で効果が高まる
- マンション足音苦情は管理組合でも受付
- 根本対策は住民同士の相互理解と配慮
さらなる『上質』をあなたへ。
「家族で庭バーベキューを楽しみたいけど、近所迷惑にならないか心配です」
そんな悩みをお持ちの方は、住環境そのものを見直してみてはいかがでしょうか。
株式会社アイム・ユニバースの『&RESORT HOUSE(アンドリゾートハウス)』なら、広々とした屋上テラスのある物件も多数取り扱っています。開放的な屋上スペースでバーベキューを楽しめば、煙や臭いの問題も軽減できます。
この機会に、あなたの理想の住まいを見つけてみませんか?
こちらの記事では住宅購入に関する疑問や課題について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事